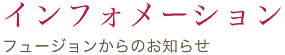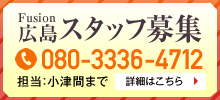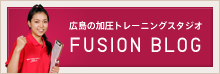■ はじめに:外部指導、本当に意味がありますか?
あなたのチームや選手は、トレーナーや医療従事者から外部指導を受けていますか?
「OBの先輩だから」「経験者だから」「有名選手の知り合いだから」という理由でお願いしているケースは少なくありません。
もちろん、それで成果が出ているならとても良いことです。
ですが、現場での様子を知ると、「もっと効果的な方法があるのでは?」と感じるケースもあります。
■ 外部指導が練習の延長線のケース
例えば、加圧トレーニングでいうと、あるスポーツチームに外部トレーナーが入り、加圧ベルトを巻いた状態で普段の練習(アップや競技動作、ダッシュなど)を行わせていたという話を聞いたことがあります。
確かに加圧ベルトを巻けば負荷はかかりますし、筋肉の張りも感じられます。
ですが外部指導では、いつもの練習に負荷を足した"負荷遊び"ではなく、その時間でしかできない「トレーナーだからこそ提供できる価値」をもっと活かすべきだと私は考えます。
■ コーチにはできない、外部トレーナーの役割
私が考える外部トレーナーの役割は、「監督やコーチが持っていない知見を提供すること」です。
競技経験に基づく指導は貴重ですが、チーム内のコーチと重なる部分も多いものです。
だからこそ、違う角度からチームを支えることが必要です。
私の場合、セラピストでもあるため、怪我予防やコンディショニングを含めて「鍛える」と「ケアする」を同時に提供できます。
■ 子ども扱いしない理由
短期的にスポーツを楽しむだけなら、「監督やコーチ、トレーナーの言ったことをそのままやる」で十分です。
しかし、上級アスリートやプロの世界になると、
-
自分の身体を自分で理解し
-
どうなりたいかを監督やコーチ、トレーナーに伝え
-
必要なものを引き出していく
といったアグレッシブな対応が求められます。
だからこそ、私はキッズアスリートに対しても一人の人間として、自分の頭で考え行動する習慣を持ってほしいと考えています。
そのために、説明を端折らず、理解できる言葉で伝え、主体的に取り組める環境をつくります。
■ 成長を体感させる工夫
成長期のジュニア選手は、身長の伸びに伴い手足が重くなり、自分の体を思い通りに扱いにくくなります。胴体が手足の動きに耐えきれず、十分な力を発揮できないこともあります。
この時期に体幹を鍛えておくことで、自分の動きに振り回されなくなりますが、体幹だけを硬く鍛えると動きが固くなり、怪我のリスクも高まります。
そのため「強くしなやか」な身体を作ることが重要です。
具体的には、
-
ボディコントロールを体得するトレーニング(デッドリフト、スクワットなど)
-
片足支持やバランス能力を鍛えるトレーニング(片足スクワットなど)
-
スポーツ動作に必要な多面的な動きへの応用(ランジ+ツイスト、ランジ+オーバーヘッドプレスなど)
■ 実例
以前指導したジュニアキックボクシング選手には、体重80kgの私と50kgの選手で押し相撲を行い、トレーニング前後の変化を評価しました。
最初は全く歯が立たなかったのに、今では体重差30kgの私が勝てないほどの力を発揮するようになりました。
これは体重差を超えるための“潜在能力の解放”を体感した瞬間です。
また、体幹の必要性を理解してもらうため、長い棒を振り回すデモンストレーションを行い、遠心力やてこの原理を体感させました。
「だから体幹が必要なんだ」と納得した選手は、トレーニングに主体的に取り組むようになります。
■ まとめ:外部指導の選び方
外部指導を依頼する際、基準は「経験者かどうか」だけでは足りません。
-
チームのコーチにはない知見を持っているか
-
鍛えるだけでなくケアや怪我予防もできるか
-
選手の理解と主体性を引き出せるか
もし今、外部指導の成果に疑問を感じているなら、一度立ち止まって見直してみてください。
私たちは、現場主義と科学的アプローチを両立させ、チームや選手の可能性を最大限に引き出すお手伝いをします。